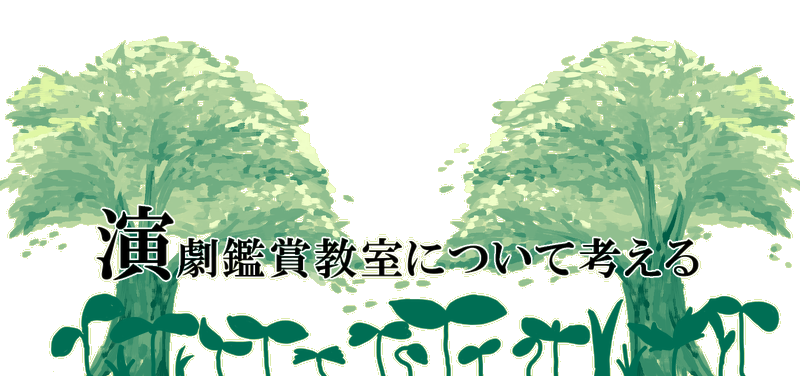
第一回
「演劇の持つ批判的想像力を信じて」
熊本大学教育学部准教授 木村 浩則
「演劇の持つ批判的想像力を信じて」
熊本大学教育学部准教授 木村 浩則
学校における演劇鑑賞教室は今や危機的状況にある。日本劇団協議会の調査によれば、学校における鑑賞公演回数は、小・中・高合わせて1999年には18,160公演であったものが、 2003年には9,615公演と、4年間で半分近くに減少している。その要因としては、少子化による生徒数・学校数の減少、学校5日制の実施による時間数の削減などがあげられている。 それでも学校関係者の鑑賞教室に対する期待は変わらないというのが劇団側の分析だが、その期待も、全国一斉学力テストによる学校間競争と教育市場化の激流にかき消されようとしている。 また学校教育の重点が「鑑賞」から「表現」に変わってきたことも気にかかる。

※「翼をください」
作・演出=ジェームス三木
1990年〜2000年 通算1050ステージ
撮影:蔵原輝人
作・演出=ジェームス三木
1990年〜2000年 通算1050ステージ
撮影:蔵原輝人
このような中で、いかにして演劇鑑賞教室の灯を守り続けていくのか。そのためには、これまで十分に深められてきたとは言いがたい鑑賞教育の意義を、青少年の今日的な発達課題、 彼らを取り巻く文化・メディア状況の中で、あらためて理論化していくことが必要であろう。 しかしながら、それが演劇関係者の内輪の議論にとどまる限り、外部からは自己保身の論拠にしか映らないだろう。 演劇や教育関係者はもとより、心理学や社会学の専門家など多様な立場や専門性の方々を巻き込んだ、 より開かれた議論の場が求められ、まずはこの特集がその仕掛けの一つとなることを期待したい。
さてそろそろ本論に入らねばならないが、今のところ私には、教育学研究者の立場からこの議論に参加するだけの準備がない。 ここでは私の個人的体験から、危機にひそむ希望の在り処を探ってみたいと思う。
私と青年劇場との出会いは、1991年の※「翼をください」公演の時期にまでさかのぼる。当時私は、熊本の私立普通科高校に勤めていた。 そこには、このお芝居同様、学校格差の偏見に苦しむ多くの生徒たちがいた。 ある教育雑誌で、青年劇場という劇団が「翼をください」を公演していることを偶然知った私は、すぐさま事務所に電話をかけた。 そして翌年、わが校ではじめて演劇の鑑賞教室が行われることとなった。予算は例年を大きく上回ったが、担当教師の熱意と協力もあってなんとか実現にこぎつけた。 学校公演は、生徒たちだけでなく、市民のあいだにも大きな反響を呼び、その翌年には高校生と市民による実行委員会形式の一般公演へと発展していった。
私と青年劇場との出会い、そして学校公演、一般公演の成功を導いたものは、鑑賞教育についての認識でも、劇団に対する評価でもない。 「翼をください」という作品それ自体である。どんなに公演環境が厳しくとも、子どもたちや教師の切実な要求に応え、彼らの琴線に触れる作品であれば、 いかなる努力をしてでも実現したいと思う教師がきっと現れるはずだ。あの作品の記録的な普及実績を支えたのは、高校生、父母、教師たちの「これは自分たちのことだ」という共感の声であった。 いま全国の子どもや教師たちは、どんな課題を抱え、何を切実に求めているのか。演劇創作者に求められているのは、その思いを聞き取り、それに正面から応える作品を生み出すことではないか。 そのような作品との出会いを通じて、彼らはあらためて演劇鑑賞の意義を理屈ではなく実感をもって認識していくのではあるまいか。
競争と格差がもたらす不安社会の中で、無力感といらだち、殺伐とした気分が、若い人々の間に蔓延している。ファシズムはこのような気分を栄養分にして肥え太る。 「美しい国家」という新しい首相のフレーズは、戦争を究極の芸術あるいは美学だとするファシストの思想を想起させる。ベンヤミンはそれを政治の耽美主義と呼び、「芸術の政治化」をもって対抗しようと訴えた。 それを私は「批判的想像力」と言いかえたい。今を生きる青少年の苦悩に寄り添い、演劇の持つ「批判的想像力」を信じる劇団と教師が存在する限り、演劇教室の灯は消えるはずがない。
(2006年10月)
現在、文京学院大学人間学部教授
※執筆者の冒頭の肩書は、当時のままになっています。
現在の肩書が分かる方は、文章末尾に表記しています。
「演劇鑑賞教室について考える」のトップページへ
青年劇場のトップページへ